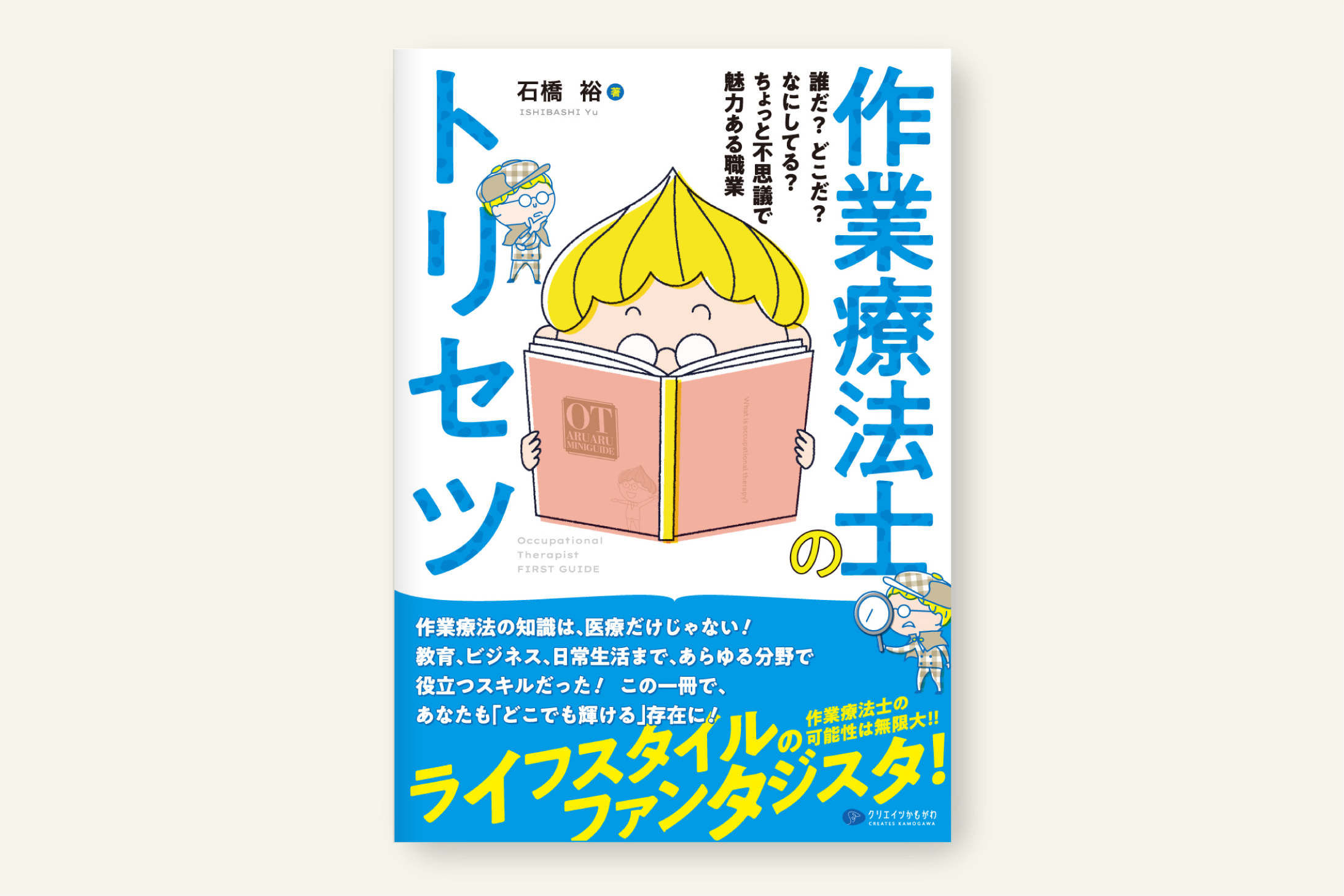なかがわ
なかがわこんにちは!
茨木市の保育所等訪問支援事業を行っている「えんりっち」の中川です。
「なぜ、医療職である作業療法士が学校に来るの?」
「訪問を打診されたけれど、一体何をしに来るんだろう…」
「保護者として利用したいけど、先生に提案して嫌がられないだろうか?」
今、全国で広まりつつある「学校作業療法」。
しかし、その専門性ゆえに「何をする職種なのか分かりにくい」のも事実。知らないことに不安を覚えるのは、当然のことです。
この記事は、その不安を少しでも軽くするために執筆しました。
作業療法士が「どういう流れ(プロセス)」で学校を訪問し、支援が必要な子どもに対してどのような「専門的視点」を持ち、「どういった支援(サポート内容)」を提供するのか。
それを知ることで、作業療法士が「評価者」ではなく、先生や保護者と共に歩む心強い「サポーター」であることがご理解いただけると考えています。
ぜひ最後までご一読ください。
なぜ今、教育現場に作業療法士が?
増加する「支援が必要な子ども」と現場のニーズ
教育現場では、特別支援をうける児童生徒の数は増加を続けており、平成5年度と比較して、平成26年度では特別支援学級に通う小学校段階の児童は2.1倍、中学校段階の生徒は1.9倍となっています。
さらに令和4年に実施された調査では、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒のうち、「知的発達に遅れはないものの学習面または行動面で著しい困難を示す」とされた児童は小・中学校では全体の約8.8%、35人学級では言えば、約3人が当てはまるとされました。
 なかがわ
なかがわこのような状況の中、教育現場で何らかの支援が必要な児童が増えていること、またその支援に対応するためのノウハウやマンパワーが必要になってきていることは明らかです。
そのため、学校現場での作業療法士の活用「学校作業療法」が広まりを見せています。


では実際に、作業療法士が学校に訪れて何をするのか?をお話していきます。
学校訪問で「作業療法士」は具体的に何をする?
サポートの「内容」と「流れ」
学校に作業療法士が訪問すると聞いて、「具体的に何をするのだろう?」と疑問に思うかもしれません。
えんりっちでは保育所等訪問支援事業を活用して作業療法士が学校訪問をおこないます。
この章では、そのサポートの具体的な「内容」と「流れ」を解説し、先生や保護者の皆さまの疑問にお答えします。
作業療法士は先生の「評価者」ではなく「サポーター」です

まず、一番にお伝えしたいのは、作業療法士は、先生の「評価」ではなく、「サポート」をする立場です。
作業療法士は医療系の国家資格でありますが、病院等の医療機関だけではなく、介護・福祉施設(子どもから高齢者まで)や教育機関、行政機関、司法機関、一般企業などの幅広いフィールドでその医療的な知識を活用し、対象の方の「その人らしい生活」を応援しています。
作業療法は一番にその人が「どうなりたいか」「どうありたいか」を把握すること からスタートします。
学校訪問でも、先生の指導についての良し悪しを「評価」するのではなく、子どもを中心に据えながらも、先生の「こうしたい」を叶えるため、良き相談相手になれることを目指しています。
学校訪問の主な流れ:観察・ヒアリング・環境の提案
はじめは保護者からのご依頼で始まります。
保護者より生活上の課題や訪問支援に関するご希望をお伺いし、えんりっちより施設様に連絡をすることから訪問支援がスタートします。
実際のお子さまの生活や行動を観察します。先生が感じる気がかりな点やお子さまに期待することなどをヒアリングし、観察で得られた情報と照らし合わせながら目標や支援内容について検討します。
保護者の希望、先生との打ち合わせを基に個別支援計画を作成します。半年間の目標と具体的な支援内容を設定し、保護者・先生・えんりっちの三者で共有します。
月に1回程度、継続して訪問支援をおこないます。子どもの観察と支援方法に関する相談を行います。定期的に訪問することで支援の効果の検証や、より効果的な支援方法の検討、また目標達成に向けた進捗の確認などを行いつつ、子どもの成長を共有します。
先生方も忙しい業務の時間を縫って相談時間を設けていただいております。可能な限り先生方のご予定に合わせるため、いろいろな形で相談時間を設けています。
- 観察しながら立ち話で相談
- 観察後、別室で20分ほど相談
- 午前中に観察、放課後時間に相談(対面・電話ともに可)
先生とは異なる専門性。生活すべてを「作業」と捉える作業療法士(OT)独自の視点
訪問の具体的な流れを解説しましたので、次は作業療法士(OT)がどのような専門的な視点を持っているのか、その核心に迫ります。
少し専門的な話になりますが、作業療法士(OT)をより深く理解していただくために最も重要な部分ですので、順を追って解説していきます。
なぜ作業療法士(OT)は「分かりにくい」と言われるのか?
実は他のリハビリテーション職種(理学療法士や言語聴覚士)と比べて、作業療法士(Occupational Therapist、以下OT)って何をしている職種なのかわかりにくいと言われることが多いのです。
 なかがわ
なかがわなにせ「作業療法士のトリセツ」という本を自ら出版するぐらいです。
なぜわかりにくいかというと、対象とする範囲がとても広いこと、そして名称である「作業」という言葉が何を指すのかイメージしにくいことにあると思います。
OTが捉える「作業」とは、朝起きてから夜寝るまでの「すべての生活行為」

日本作業療法協会の定義は以下の通りです。
作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す。
日本作業療法士協会 https://www.jaot.or.jp/about/definition/
作業と聞くと軽作業、事務作業のような行為を指すことが多いですが、作業療法の定義では「作業とはー生活行為を指す。」とあるように、朝起きてから夜寝るまでにおこなっているすべての活動です。
例えば私の場合、朝起きてから、服を着替え、食事をして、洗濯をし、子どもを見送り、車の運転をし、PC作業をし、子どもたちと遊び、同僚とコミュニケーションを取り、お風呂に入り、子どもに絵本を読み、寝かしつけをし、TVで録画番組をチェックする…とこの一つ一つが作業です。
「できる」ことが、その人の「健康」と「幸福」を支える
「対象となる人々にとって目的や価値を持つ」という部分は、私の場合、社会の中で父という役割や作業療法士、会社の代表という役割を担っています。
 なかがわ
なかがわもし、右手が動かなくなってしまえば、車の運転やPC作業、子どもと遊ぶことは困難になるかもしれません。
生活の中で何かができる、できないということは、単純な能力だけでなく、社会的な意味やその人の人生の意味にも影響を与え、「健康」や「幸福」に大きな影響を与えます。
多様な背景を持つ子どもが多くなっている現代では、先生方は最大限「個」を尊重しながら集団運営をされています。
その中で、「なぜこんな行動をとるの?」、「なぜできないの?」と悩まれることも増えているのではないでしょうか?
「なぜしている?」「なぜできる?」この2つの視点で効果的な支援の鍵

お話したように、私たちは自分たちが持つ価値観や意志、役割から作業を選択し、作業の方法を選択し、その作業が達成されることで社会的な意味を感じ生きています。
例えば、子どもが座ってお話を聞いているのは当たり前ではありません。
そうすることが「良い」と感じ行動する価値や意志、クラスの一員としての社会性やアイデンティティ-が育っているからできるのです。
それが何らかの理由で叶わない時、つまり「できない」とき、子ども達は大人が「問題」と感じる行動を取ることがあります。
しくしくと泣いたり、怒ったり、部屋を飛び出したり、挑戦しなかったり、乱暴になったり
つまり「している(したい)」と「できる」にギャップがあるとき子ども達のこころは困ります。
「したい」は人の心なので、変えることはできませんが、「できる」は変えられます。
なぜなら、作業療法士は「できる」も分析するからです。身体面から認知面から、コミュニケーション面からお子さんの作業遂行を分析して、どこに課題があるのかを発見、それを先生に伝えながら、サポート方法を一緒に考えます。
「したい」が「できる」とき、子どもたちは一番の達成感と満足感を感じ、その人らしい人生を謳歌します。
 なかがわ
なかがわそんな子どもの姿を見るのが保護者、先生、そして私たちのかけがえのない喜びにもなります。
私たちはこの2つの視点を活かして捉えた子ども像を先生に伝え、お子さまの支援をサポートします。
OTの役割:「訓練」ではなく、「できた!」が適う「環境のデザイン」
この「その人らしく」を科学する職業だからこそ、教育現場や保育現場の先生方と効果的にコラボレーションし、子ども達の成長に寄与できると考えています。
作業療法士は医療職としての専門知識や技術を持ちながら、それを生活や人生の営みという視点で活かすことができます。
先生方がおこなう教育活動、保育活動の中にある、子どもたちの生活や遊び、子ども同士の関り、そして勉強など、教育現場や保育現場に溢れているこの作業たちを専門的な視点で分析し、「できた」が適うように、作業のやり方や環境を対象となる方と一緒にデザインしていく。
冒頭で私は「作業療法士は何をする職種なのか分かりにくい」と書きました。
その理由は、まさにこの「医療の視点」と「生活の視点」を掛け合わせ、ご本人と一緒に未来をデザインしていく、というアプローチにあるのかもしれません。
そこに、私たち作業療法士だからこそできることがあります。
 なかがわ
なかがわでは次に、実際におこなった「環境デザイン」のアプローチの事例をご紹介します。
事例1(姿勢):やる気がないのではなく、座りにくいから?

授業中、いつも机に伏せているAさん。担任の先生は「姿勢をぴんとしてください」と声をかけます。その時は姿勢が直るのですが、しばらくするとまた姿勢が崩れてしまう。
先生からは「何度伝えても聞いてくれない。やる気がないのか?私のことが好きじゃないのかも?」とご相談がありました。
支援員が訪問に伺い、授業での様子を観察しました。
Aさんの姿勢や机や椅子の状態を確認したところ、Aさんは姿勢を保つ力が弱く、骨盤(腰からお尻の部分)を立てておくことが難しいことがわかりました。また、骨盤が後ろに倒れることで、だんだんとお尻が前にずれてしまい、姿勢が崩れるようでした。
Aさんの姿勢の崩れは軽減し、先生の声掛けで姿勢を正せることも増えてきています。
事例2(不器用):本人の努力不足ではなく、目や手の使い方が難しいから

授業中、板書をあまりしたがらないBくん。先生が「早く書こうね、間に合わないよ」と促すと写し始めますが、スピードは遅く、授業の時間内には間に合いません。
先生からは「Bくんはいつも板書が間に合わず、急かしても伝わっていないのかいつものんびりしています。やる気がないのかな・・・」と相談がありました。
支援員が訪問に伺い、授業中の様子を観察しました。
確かに板書にはなかなか取り組まず、時間がかかっています。鉛筆を持つときには指先では持っておらず、握りこんでいて、肩が挙がっています。しかし授業中にプリントからノートに書き写す作業では、板書よりも早く取り組めていました。
Bくんは手先の動かし方が不器用で、眼球の動かし方にも特徴があることがわかりました。左右にはスムーズに動くのですが、上下や遠近の調節がとても難しいのです。
Bくんは以前より、書き写す時間が早くなってきました。また、先生がBくんの不器用さを理解されたことで、板書だけでなく、宿題の書字量を調整され、本人にとって無理のない範囲で学習に取り組めるようになりました。
事例3(集団):話を聞いていないのではなく、学習のスタイルが異なるから

園庭での活動が終わり、担任の先生から次の行動の指示があります。
「お茶を飲んだら、水筒とトレーナーをもって教室に帰ります。荷物を片付けたら、トイレに行きたい人はトイレに行って、次は給食です」
そのお話を聞いたみんなは一斉に動き出しますが、Cくんはお茶を飲んだ後、座ったままでのんびりしています。
先生が気づき、「Cくん、お話聞いていた?次は何をするの?」と尋ねますが、Cくんは「わからない」と答えます。
先生からは「Cくんはいつもお話を聞いていないので、集団での行動が上手くできません、どうやったら聞いてくれるのか・・・」と相談がありました。
支援員が訪問に伺い、クラス活動の様子を観察しました。お話を聞けないとの相談でしたが、製作活動では、先生の説明を聞いてみんなと同じペースで完成できていました。その時先生は工程ごとに見本をつくり説明をしていました。
その様子から、Cくんは、耳から聞いた情報を覚えておくことが難しく、目で見てわかる手掛かりがあると理解しやすいことがわかりました。
このように「やる気がない、努力をしない、話を聞かない」と思われる行動の原因は、「姿勢が保てない、目や手の動かしかたが違う、情報の取り入れかたが違う」という特性からであることと、その特性を環境で補うことで「できる」ようになることが、事例からおわかりいただけたかと思います。
まとめ:作業療法士は、先生と共に「その子らしさ」を支えるパートナー
私たち作業療法士は、対象となる人々が、「その人らしく」暮らし、生きていくためのサポートをする職業です。
この壮大さがはたまた具体的に何をしているのかわかりにくいということにつながっているのかもしれません。
一見するとわかりにくいですが、一旦お付き合いを始めると、肌で良さを感じてもらえるのが作業療法の特徴です。諸先輩方の地道な活動が実を結んで広がりが見え始めているのが、現在の学校作業療法の状況なのかもしれません。
作業療法士は、先生方と共にお子さまの成長を支える強力なパートナーとなります。
具体的な訪問支援サポートにご興味を持たれた方へ
この記事では、作業療法士(OT)の学校訪問における役割や視点について解説しました。
もし、先生ご自身の園や学校、あるいは保護者としてお子さまのために、具体的なサポートの利用をご検討されたい場合は、私たちが提供する「保育所等訪問支援サービス」について、ぜひ詳しくご覧ください。
「まずは情報収集だけしたい」「管理職にどう説明すればいいか相談したい」といった段階でも、もちろん大歓迎です。作業療法士がお話を伺い、それぞれの園や学校に合った活用の形を一緒に考えます。
「利用するにはどういう手続きが必要?」「料金は?」といった具体的な疑問にお答えします。園や学校に相談する前に、まずは専門家の話を聞いてみたいという方も、お気軽にお問い合わせください。